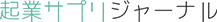従業員を雇用する際には、雇用契約を締結することになりますが、会社側で雇用契約書を作成し、新入社員に示すのが実務上の一般的な流れであると思います。
本稿では、雇用契約書を作成する際に、最も注意をしておきたい4つのポイントを説明させて頂きます。
雇用契約の期間の定めの有無
第1は、無期契約か有期契約かという、雇用契約の期間の定めの有無です。
期間の定めが無い場合は、会社側から雇用契約を終了させる場合は解雇の手続を取らなければなりません。解雇を行った場合には、解雇された元従業員から解雇無効訴訟を提起されるリスクがあります。
期間の定めがある場合は、契約期間の満了時に、契約を更新しなければ合法的に雇用契約を終了させることができ、解雇時のようにトラブルになることも原則としてはありません。
有期契約と類似する概念に「試用期間」があり、試用期間内であれば会社の判断で、自由に解雇をすることや、試用期間終了時に本採用を拒否することができると考えている経営者や人事担当者の方も少なくないようです。しかし、我が国の労働法における試用期間は、「解雇規制が若干緩和されている」にとどまり、試用期間の勤務成績や勤務態度がよほど不良で無ければ解雇や本採用拒否をすることができません。
ですから、採用時の能力や人柄が未知数で、いったん様子を見たいという場合は、試用期間ではなく、有期契約を結ぶことをおすすめします。
また、雇用契約書で、期間の定めを特段行わなかった場合には法的には無期契約という扱いになりますので、有期契約を意図している場合は、必ず契約期間の明記を忘れないようにしてください。
職務内容・勤務地の変更の可能性
雇用契約書には、職務内容や勤務地を記載する欄があります。
通常は、採用当初の職務内容や勤務地が記載されますが、その後の人事異動で職務内容の変更や勤務地の変更が想定されることが一般的だと思います。
その旨が雇用契約書に記載されているかということが重要なチェックポイントです。
雇用契約書に「職務内容の変更を命じる場合がある」「勤務地の変更を命じる場合がある」という記載が無い場合には、本人が拒んだ場合、職務内容変更や転勤の辞令が法的に無効となる恐れがあります。
というのも、職務内容や勤務地の変更がある旨が雇用契約書に示されていないと、本人が「私はこの職種以外は嫌です」「転勤をしたくありません」と主張した際に、会社側にそれを人事権として命じる法的根拠が得られなくなってしまうからです。
会社側としても、職務内容や勤務地の変更を想定しない前提で採用したのであれば問題無いのですが、変更の可能性を含んでいる場合は、その旨を、必ず雇用契約書に反映させてください。
固定残業代
「基本給には45時間分の固定残業代を含む」「基本給に50,000円分の固定残業代を含む」といったように、基本給に固定残業代を含んだ雇用契約を締結することは少なくないと思います。
その際、雇用契約書には、時間数か金額、いずれかで、基本給にどれだけの固定残業代が含まれているかを明記しなければなりません。
明記をしていないか、「基本給は残業代込みとする」というような時間数も金額も記載がないような形ですと、残業代未払いで裁判になったり、労基署の調査が合ったりした際には、固定残業代は無効となってしまいます。
無効となった場合、時効消滅した分を除き、全ても残業代を精算しなければならなくなってしまいますので、固定残業代を導入する場合は、必ず雇用契約書上に、時間数か金額を明記するようにしてください。
懲戒解雇
懲戒解雇を含む、懲戒処分を行うためには就業規則上の明文の規程が必要なのが原則です。
雇用契約書上では、解雇については「就業規則の定めによる」と書かれていることが一般的ですが、10名未満の会社などで、就業規則を作成していないにもかかわらず、ひな型のまま「就業規則の定めによる」という文言を残してしまうことは危険です。
「就業規則の定め」が存在しないため、法的に懲戒処分を行うことができなくなってしまうからです。
対策としては、まずは簡易的なものでも構わないので早急に就業規則を作成するか、懲戒処分の対象となる事由を雇用契約書に列記し、雇用契約書だけで懲戒処分に関する記載を完結させれることです。
まとめ
本稿では、雇用契約書の作成時の最重要チェックポイントを4点紹介させて頂きました。しっかりとした雇用契約書を作成しておくことが、万が一の労使トラブル時の対策となりますので、是非、自社の雇用契約書の記載内容の再チェックと、必要に応じ、修正をお願いします。