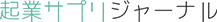既に私たちの生活に欠かせないオンライン上の電子商取引(EC)ですが、近年、ライブコマースという新しい形態が広まってきています。日本におけるライブコマースの牽引役として、ライブコマーサーのプロデュース・マネジメントを行う専門事務所「トキバナ」、ライブコマースプラットフォーム「WABE」の運営などを行う株式会社Cellest代表の佐々木さんに起業の経緯や今後の展望について、お話を伺いました。
―まずは、どのような事業を行われているか、教えてください。
当社は現在、ライブコマースというビジネスを主軸に展開しています。ライブコマースとは、ライブ配信とECを組み合わせてリアルタイムで商品を販売する手法のことで、いわば「スマホ版のテレビショッピング」のようなものです。配信者が視聴者と双方向にやり取りできるのが、テレビショッピングとは明確に違うポイントです。そして、ライブコマースで配信を行うプレイヤーのことを「ライブコマーサー」と呼ぶのですが、私たちはこのライブコマーサーのプロデュースとマネジメントを行う専門事務所「トキバナ」と、ライブコマースに特化したプラットフォーム「WABE」の運営を行っています。
現状では、当社がマネジメントするライブコマ―サーはTikTokライブを活用してライブコマースを実施していますが、今後は「WABE」と併用しながら展開していく見込みです。 ライブコマーサーの方は雇用または業務委託する形で、実際に販売を行っていただく、という形で事業を展開しています。自社でセレクトショップを運営しているイメージですね。商品を仕入れて、それを販売するライブコマーサーはいわば店員、という形です。
―起業の経緯を教えてください。
実は私、高卒で一度就職したんです。18歳の時に就職して、20歳の時に脱サラして1年間勉強して、同志社大学に入学しました。入学後すぐに、関関同立向けの専門塾で起業しました。その後、メルカリで物販をするようになったのですが、2017年にメルカリにライブコマースの機能が実装されたんです。「面白そうだな」と思ってやってみたところ、すごく売れたんです。
そこからライブコマースについて調べてみると、中国や韓国など、日本以外の国ではすでに普及していて、物を買う際の選択肢として当たり前になっていることを知りました。
中国まで視察に行くと、衝撃的でした。街中にライブ配信者がたくさんいて、ショップの店員さんもライブ配信で物を売っているんです。店側もライブコマーサーを受け入れる体制が整っていて、ライブコマース専用の特設ブースまでありました。1時間で10億円売り上げるようなライブコマーサーもいて、その影響力は芸能人を超えるほどなんです。「自分の知らない世界だ」と、本当に驚きました。
日本にはテレビショッピングという文化があるので、これがライブコマースに置き換わって流行っていくのだろうと感じ、大学卒業後には株式会社Cellestを設立して本格的にライブコマース事業に取り組んできました。
現在の日本のライブコマース市場は、ようやく流行り始めてきた、という段階ですね。ユニクロやニトリ、資生堂といった各業界のトップ企業はすでに参入しています。ただ、ライブコマースが一般消費者の方々に広く認知されているかというと、まだこれから、という状況です。既にライブコマースの影響を受け始めているけれど、そこまで強く意識している訳ではない、という印象です。
―起業について、苦労されたことはありますか。
よくインタビューでは聞かれるのですが、起業における苦労は特にありません。自分でも、メンタルが強いからそう感じるのか、本当にないのか、よくわからないのですが(笑)。スタートアップなので、もちろん色々なことはあります。毎日何かとんでもないことが起きる、みたいな。でも、私の中では、特に「しんどかった」とか「ハードシングスだった」と感じたことはないんです。労力は毎日非常にかかっています。でも、それを「つらい」「苦しい」とは感じられないんです。そういうことに一喜一憂していたら、経営者としてはやっていけない、くらいの感覚でいます。「それくらい当たり前だろう」と思ってやっているので、何が大変だったのか、あまり理解できていないのかもしれません。
逆に、やりがいを感じられたことや、学びに繋がったと感じられたことなども同様でして、日々嬉しいこともありますが、日常的に起きることなので、特に過去の出来事を振り返って「あれが嬉しかった」というのはあまりないんです。
ただ、周りの方々から「すごい」と言っていただけたことは記憶に残っています。例えば、ライブコマースの日本一を決める大会のようなものが色々あるのですが、そういう大会で優勝した時などは、嬉しいですね。過去に出場した大会では、ありがたいことに全て優勝させていただいています。ただ、そういう場合でも、勝った瞬間は嬉しいのですが、「また明日から戦わなければ」という気持ちになるので、常に気を引き締めています。
―ありがとうございます。こういった経営者としてのスタンスは、どのように得られたのでしょうか。
私は小学校1年生くらいの時から起業したいと思っていたので、割と早い段階からこのスタンスが身に付いたのかもしれません。幼い頃から、今のように落ち着いていると言われて育ちました。特に親が経営者だった、というわけではないのですが、小学生や中学生の頃から、社会のシステムに対して「非効率だな」と感じることが多かったんです。例えば、学校の授業って退屈だけどずっと受けていなければならないとか。社会人になってからも、朝決まった時間に出社して、定時に退社する、というような働き方や、上司や部下といった組織構造、メールのやり取りなど、様々なことに非効率さを感じていました。「もっと効率的にできるのに」と、常に思っていたんです。そういう思いを持ち続けていたので、幼い頃から大人びていたのかもしれません。周りの子より少し頭が良い、という自覚もありました。漢字も算数も早くから理解できて、暗記力も良かったので、あらゆる教科が得意だったんです。そのため、「自分は人よりできる」という感覚を早くから持っていた、というのも大きかったと思います。
それで、クラスの中ではリーダー的な存在で、色々な人をまとめていたので、「こうすれば人は動くんだ」ということを早くから理解できました。経営学を直接学んだわけではないのですが、コミュニケーションを取る上で、「どうすれば人は喜ぶのか」「どういうことをすると嫌がるのか」「どうすれば人がついてくるのか」といったことを、学校で具体的に学んでいたように思います。
中学を卒業してアルバイトができるようになってからは、色々なアルバイトを経験しました。サービス業、例えば飲食店のアルバイトなどをして、「どうすれば喜んでもらえるのか」「どういうことをすると嫌がられるのか」「なぜこの店は流行っているのか」「なぜ流行っていないのか」というようなことを、常に考えていました。こういったことは、誰かから学んだり、本を読んだりしたわけではなく、自分の頭で考えていました。
マーケティング的な観点も幼い頃から考えていました。何か商品一つ買ったときに、「なぜこの商品を買ったのか」というのを考える癖がついていて、「何と迷って、なぜ買ったのか」、そして「やめたものがあれば、これはなぜやめたのか」というのを常に考えています。 例えば、水1本買うときに、「今何で自分は水を買ったんだろう」みたいな。いろんな水が置いてある中で、また横にはお茶やコーラが置いてある中で、なぜかある一種類の水を僕は取った。この時、何と迷ったんだろうか。天然水の中で迷うパターンと、お茶と迷うパターンとコーラと迷うパターンがあって、太るから水にしとこうとか、今はお茶を飲みたくなくて、お腹いっぱいになりそうだから水を飲もうとしていたな、と。こうやって選択について考えていると、たとえ話ですが、水の販売で僕が起業しようと思ったときに、通常は水の競合を探すから、各天然水の違いを見たりするんですが、そもそも人が水を選ぶときって喉が渇いているわけなので、競合が実はコーラとかお茶だったりとかする。
そういうことを常に考える癖が昔から染みついているので、今僕たちがECをやるときに、お客さんが何と迷って、どういう購買心理でその商品を選ぶかとか、何だったらやめるかみたいな、膨大な量のパターンが頭に入っているわけです。商品を仕入れる際にそうした当て感が有効だったりします。比較検討するときに必ず言語化し、選択する際は気分で済ませず、全部説明をつけようとする、という癖付けもあるのですが、それも強みかもしれません。
こうやって、ずっと頭を使っていて、何を見ても、何か頭にワーッとひらめく感じがあって、それが経営にも役に立っています。こうした自分の考え方はメンバーにも落とし込まれていて、会社のマーケティング力として強みになっていると思います。
―子どもの時から経営者目線をもって思考をめぐらしてきた結果が、今の佐々木さんのスタンスや会社の強みを形成した、ということが伺えました。そんな佐々木さんは、今のCellestをどう見ておられますか。
今の当社については、2つの軸でお話できるかと思います。
まず、ライブコマースという軸で考えると、日本にライブコマースが入ってきたのが2017年で、私はその年からライブコマース事業を始めています。まだ「ライブコマースって何?」という人がたくさんいる中で、7年前から事業を始めているというのは、かなり早い方だと言えるでしょう。そこから色々な企業が参入してきましたが、撤退していった企業も多いです。ライブコマース事業には、色々な難しさがあるんです。しかし、私はこれまでずっとトップランナーとして、事業を継続してきました。そのため、日本のライブコマースについて調べようとすると、ほとんどの場合、私たちの会社にたどり着くと思います。プレイヤーが少ない、ということもありますが、私たちが圧倒的な実績を出している、ということも大きいですね。日本のライブコマース市場を牽引してきた、という自負がありますし、これからも、私たち以外には作れないだろうと思っています。
当社が事業をここまで継続できたのは、私自身が非常に細かい性格で、データを分析することが得意、というのが大きかったと思います。分析力があり、分析したことを実行する力もある、というのが、他社との大きな違いだったと思っています。ライブコマースにおいて、どのような発信をすれば成果が出るのか、ということを分析し、改善していく、ということを徹底的に行ってきました。
ライブコマースは、非常に大きな可能性を秘めた、便利なものです。この便利なものを日本に流行らせるのは、自分たちしかいない、と思っています。
そして、もう一つの軸が、スタートアップとしての側面です。日本は、アメリカのシリコンバレーなどに比べると、スタートアップがあまりうまくいっていない、と言われています。私も海外によく行くのですが、「日本って全然ダメだよね」と言われることが多いんです。それは、日本人特有の考え方が影響しているのだと思います。日本の良い面でもあるのですが、非効率な部分も多く、それが日本の良さを消してしまっていると感じています。スタートアップとして、世界に誇れるような企業を作っていくべきで、私たちの会社ならそれができるのではないか、と思っています。私が起業してから、色々な投資家さんやVCさん、銀行さん、事業会社さんなどにお会いする中で、「こんな会社見たことがない」とよく言われるんです。例えば、IPOに知見のある方から、既に内部が整理されていて、ほぼ上場基準をクリアしてるぐらいって言われるなどですね。それから、会社の強みについてもです。前述したマーケティング的な観点を持ち続け言語化できる力もそうですが、加えて、当社のデータを分析する力、市場を読み解く力、そしてそれを実行に移すスピード、こういった点を外部からも非常に評価していただいています。
私自身、経歴も考え方も、一般的な起業家とは少し違うのですが、色々な方に評価していただく中で、自分でも「もしかしたらすごいのかもしれない」と思えるようになりました。ただ、それが井の中の蛙なのか、本当にすごいのか、試してみたいという気持ちもあります。日本を代表するようなスタートアップになれたら良いな、と思っています。日本にはまだ数少ないユニコーン企業を目指して、5年以内に自分の会社の時価総額を1000億円ぐらいにはしようと思っています。
そして、私が成功することで、他の経営者の方々を勇気づけられたら、とも思っています。一人の若者がすごい会社を作るまでのストーリーをみんなに発信することで、世の中に勇気を与えられたら嬉しいですね。
―本日はありがとうございました。